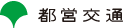

いまもなお、見番や料亭がある粋な街、向島。隅田川の東、吾妻橋から桜橋にかけては多くの神社仏閣や公園があり、東京スカイツリー®まで人気のお散歩コースになっています。『ものづくりの街 墨田』を象徴する工房ショップも点在。季節の良い10月、下町の風情を感じながらのんびり歩いてみましょう。

街歩きに便利な観光マップやパンフレットが入手できます。散策の前に立ち寄ってみましょう。

幕末に江戸城無血開城を果たすなどの偉業で知られる勝海舟。墨田区本所生まれの縁で、墨田区役所の隅田川側、うるおい広場に銅像が建立されています。

江戸時代に水戸藩下屋敷があった地で、十五代将軍、徳川慶喜もよく来ていたといわれています。明治維新後も水戸徳川家当主が代々ここに住み、立派な門や洋風建築が建てられていたようです。関東大震災で屋敷が全壊し、復興整備の際、公園になりました。庭園は水戸徳川邸内の池などの遺構を利用して造られていま す。園内には堀辰雄旧居跡もあります。

古くは向島須崎町にありましたが、関東大震災後に現在の地に再建。隅田川に沿う旧本所一帯の総鎮守として知られています。境内の「撫牛」は自分の悪い部分と牛の同じ部分を撫でると病が治るという信仰で、肉体だけでなく心も治るという心身回癒の祈願物として有名。総檜権現造りの本殿前には全国的に珍しい三輪鳥居(三つ鳥居)と「狛牛」があります。

文和年間(1352~1356)、巡礼中の近江国三井寺の僧が当地で荒れた祠の修復をしようとしたところ、地中から白狐にまたがる神像を発見。すると何処からともなく白狐が現れ、この神像の回りを三度回って消えたといいます。神社の名はこの故事に由来。元禄6(1693)年の江戸のかんばつの際には、俳人宝井其角が句を献じた翌日、雨が降り始めたという逸話があり、境内に「雨乞いの句碑」があります。江戸時代、三井家の守護社として崇拝され、現在も三井家の守り神となっています。

昭和33年創業の生ジュースと自家製くるみパンの店。昭和モダン、ノスタルジーという言葉がしっくりくる建物は、小説の神様といわれた志賀直哉の弟、志賀直三氏の設計・デザイン。バラ模様のテーブルや天井、シャンデリア、線彫りのレリーフなど、ビクトリア様式の内装は当時から来客者を魅了してきました。壁に飾られた絵画の数々は、先代のマスターが買い集めたもので、毎年掛け替えられます。通年メニューのアロエ・セロリ・リンゴなどが入った活性生ジュースや季節の果物を使った新鮮なジュースは4~5種類あり、注文してから作られます。自家製パンのサンドイッチは、くるみブルーベリーパンのナス・モッツァレラサンド400円が一番人気。テイクアウト専用のくるみパン300円もあります。

三代将軍家光が鷹狩りに来た時に腹痛に襲われ、この寺の井戸水で薬を服用して痛みが治まったことから、長命寺の寺号を与えたといわれています。境内には十返舎一九の狂歌碑、松尾芭蕉句碑、幕末の外国奉行成島柳北の碑など多くの石碑があります。

昭和24年、戦後の荒廃した時代に「少年に明日への希望」をスローガンとして誕生しました。以来、数多くの少年球児がこの球場から巣立っていき、日本が誇る世界のホームラン王の王貞治氏もそのひとり。球場へのゲートにはバッターボックスに立つ王貞治氏のプレートがあります。

すみだの特産品、文化、歴史、観光、グルメ情報を紹介するスポット。伝統工芸の職人や町工場が生み出 す“ものづくり”、雑貨や老舗の和菓子などの“特産”、歴史や文学、観光、イベント情報を発信する“まちあるき”、下町スイーツが味わえる“茶屋”の各コーナーのほか、週替わりで伝統工芸職人の実演コーナーがあり、すみだの魅力が詰まっています。“ものづくり”コーナーでは、すみだの想いを伝える商品や飲食店メニューを墨田区認証ブランド「すみだモダン」として紹介しており、一部は購入可能。“まちあるき”コーナーにはガイドが常駐し、まち歩きの相談にものってくれます。