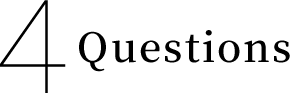車両電気部
木場車両検修所 運用区 検査班
及川 翔馬
2018年入局
幼い頃から鉄道が好きで、運転手や車掌に憧れを抱く。将来は鉄道に関わる仕事に就きたいと考え、電気科のある高校に進学。就職の際にも鉄道関連の仕事を志望し、発展を続ける都営地下鉄に魅力を感じて入局を決意した。
日々の積み重ねが、
未来の安全につながる
鉄道の「当たり前」を
支える責務
仕事と魅力
1両で約25トン
巨大な車両をミリ単位で整備する
木場車両検修場では主に都営大江戸線全線の車両検査を行っており、私が所属する検査班では一つの編成に対して3か月ごとに実施する「月検査」を担当しています。検査は大きく車両の床上と床下に分けられ、チームで作業を分担しながら、ブレーキやパンタグラフ、乗務員室や客室内など、車両におけるほぼすべての設備を点検していきます。
車両は1両あたり約25トンもの重量があり、100人以上のお客様を乗せて走ります。それほど巨大な鉄道車両を、私たちはミリ単位で調整し、整備を行っています。検査においては、チームで連携しながら多岐にわたる検査項目を点検していくのですが、小さな異変や故障も見逃さずに対処できると達成感があります。
私はもともと鉄道が好きだったこともあり、何より電車に触れられていること自体にも喜びを感じているのですが、一方で大勢のお客様の命を預かっているという責任の重みを決して忘れることなく、常に気持ちを引き締めながら検査に当たるようにしています。

想いとエピソード
日々の細かな整備の積み重ねが
10年先の安全をつくる
普段はあまり意識されない定時運行の裏側には、整備の積み重ねがあります。私たちが3か月ごとに行っている月検査を4回繰り返すと1年になります。それを地道に積み重ねていくと、10年、20年という長い年月になります。つまり、都営地下鉄の未来の安全とは、私たちの日々の仕事の積み重ねだといえます。
鉄道車両の整備という仕事は、利用者の立場からは見えにくく、私自身も働き始めるまでは想像のつかない世界でした。しかし実際に入局して、まず検査項目の多さに驚き、日々の細かな検査によって鉄道は支えられていたのだと感動すら覚えました。
毎日、同じ時間に電車が来て、無事に目的地に到着する。それは一見当たり前のことのように思えますが、私たち電車整備の立場から見れば、実は大変なことです。これからも日々の整備を丁寧に積み重ねていき、安心して都営地下鉄に乗れるという「当たり前」をつくり続けていきたいと考えています。
夢・目標
新型車両への置き換えが進む大江戸線
今後も現場で知識を習得し続けたい
大江戸線では現在、「12-600形」という新型車両への置き換えが進んでいます。新型車両は整備の手順が今までの車両「12-000形」と異なっており、電車整備としてイチから覚えることも多々あります。既存の車両だけでなく新型車両についても勉強していくのは容易なことではありませんが、トラブルがあった際に冷静に対応できるよう、今以上に知識を身に付けたいと考えています。
交通技能職の今後のキャリアとして、試験を受けて事務所の助役としてステップアップしていく道もあるのですが、私は整備の現場で電車に触れ続け、将来、リーダーとなりステップアップしていきたいと考えています。運用区検査班の班長は、経験が長い大ベテランの先輩で、車両に関することは何でも知っており、周囲からも絶大な信頼を得ている方です。以前、まるで原因が分からなかった不具合を班長があっという間に解決し、驚かされたこともありました。私もそのような存在になれるよう、鉄道整備のプロフェッショナルとしての技術を磨き、安全を支え続けていきたいです。

-
今の仕事、「ここを見てほしい」といえば?
消耗したブレーキライニングの交換作業です。この作業で不備があれば重大事故にもつながりかねない、特に緊張する作業の一つです。ブレーキライニングは、お客様の命を預かる鉄道においてもっとも重要な部品といっても過言ではありません。だからこそ、絶対にミスを起こさないよう、基本的な作業順序を慎重に確認しながら、一つひとつの作業を丁寧に行うことを心がけています。
-
プライベートは何をしている?
実は鉄道だけでなく自動車も好きで、プライベートではドライブを楽しんでいます。休暇は十分に取得できる環境であるため、先の予定も立てやすいですね。
-
入局して一番成長したところは?
わからないことがあればすぐに図面を見たり、先輩に質問したりしています。私自身、まだまだ知識不足ですが、日々勉強を続けているおかげで、後輩から質問を受けた際に、すぐに答えられるようになってきました。
-
未来の仲間に一言
鉄道に関する知識はなくても構いません。先輩方が丁寧に育ててくれる働きやすい環境なので、少しでも興味がある方はぜひチャレンジしてみてください。

-
8:30
始業
検査班で集まって点呼を行い、当日の検査内容や自分の担当作業について確認します。
-
9:00
各種機器の点検
チームで分担し、戸閉装置(ドアエンジン)、非常通報装置や空調の制御盤、屋根上のパンタグラフ、床下のブレーキなどの点検・清掃を行いつつ、消耗材のブレーキライニングなどの交換・整備も行っていきます。客室内の点検の際には、お客様が触れる手すりなどに緩みがないかチェックします。お客様が怪我をしないよう、手を触れる可能性がある箇所には破損やビスの飛び出しがないか、特に気を付けて確認しています。
-
10:30
絶縁試験
点検・清掃が一通り完了したら、車両に実際に電気を流し、不正な電流が流れていないかどうかを確認する絶縁試験を行います。
-
12:00
昼休憩
午前の作業が終了し、各自昼食を食べながら休憩を取ります。
-
13:00
ドア試験
車両のドアに物が挟まった際には、運転台のパイロットランプが点灯する仕組みになっています。ドアの不具合は重大事故につながりかねないため、実際に検査用の板をドアに挟みながら、ランプが問題なく動作しているかどうかのチェックを行います。
-
14:00
模擬環境上の動作確認
車両検査システム装置により、模擬的な走行環境を用意します。実際に走行している時と同じような環境を作り、ドアや車両の制御システムなどが正確に動作しているのかどうかを確認します。
-
15:30
サービス機器類などの動作確認
放送装置の音量確認、空調装置の動作確認、表示灯類の点灯確認などを行います。
-
16:30
力行試験
検査の最終工程として、実際に走行させてみて、制御装置やブレーキ装置に不具合がないかどうかをチェックします。
-
17:15
業務終了・退勤
1編成(8両)すべての検査を1日で完了させ、問題がなければその日の作業は終了となります。
![交通技能[電車整備]](../assets/img/work/person08_h1.png)