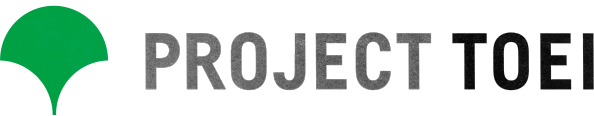青木淳さんに都営交通を巡っていただき、その使われ方を考察していただくこの連載。今回は、東京さくらトラム(都電荒川線)の停留場のベンチがテーマ。そのありうべき姿を、4回にわたってお届けします。
第3回モックアップでの検証




ーーできましたね。
青木淳さん「このモックアップで、使う人の立場で立ち上がったり座ったりするときに不自由がないかどうか。座ったり立ったりしながら確認していきましょう。」
ーー(座りながら)いいですね。なぜか落ち着く。この端にも座って大丈夫ですか?
青木淳さん「片方から支えてその先が突き出ている、いわゆる『持ち出し』になっているけれど、そこにも座れますよ。」
ーー手すりも気にならないですね。隣と人との程よい境界にもなっているし。
青木淳さん「ベンチの高さはどうでしょう。長時間座るベンチなら低い方が楽ですが、立ったり座ったりすることが多い停留場のベンチだと、ある程度高い方が、高齢者にとってはいいでしょうね。もちろん、高すぎると足が地面に届かないけれど。とりあえず今回試してみた42センチというのは普通の椅子の高さ。」
ーーちょうど良い高さですね。ちょっと座って、電車が来たらすぐ立ち上がるということでいうと。あまりリラックスしすぎてもおかしいでしょうし。それにしても美しい。
青木淳さん「構造体がそれぞれ独立して立っていて、そこに木を渡しているだけ。ふつうだと構造体同士をつなぐ梁のような材料を入れます。その方が柱に相当する手すりを細くつくることができて、力学的には合理的です。でもそうすると、何が何を支えているのかが曖昧になってしまって、見た目はヌルくなる。ダサいんです。」


ーーあと木にしてよかったですね。これも一本ずつ独立しているのでしょうか。
青木淳さん「はい。4本ある木がそれぞれ独立して構造体に留めています。だから一本ずつ取り替えることもできます。この大きさだったら間伐材も使えますし、手に入りやすい大きさになっています。」




ーー実際には液体ガラス化した多摩産材檜を使う予定ですね。
青木淳さん「はい。いまはモックアップだから違う木材を使っていますが、東京の木が使えるといいですね。」
ーー座り心地、ちょうど良いですね。
青木淳さん「高さ、大丈夫そうでしょうか。」
ーー大丈夫そうですね。
次回は試しに停留場に実際に設置してみましょう。
-
- 青木 淳(あおき じゅん)
-
建築家。青木淳建築計画事務所を主宰。青森県立美術館などの公共建築、住宅、一連のルイ・ヴィトンの店舗などの商業施設など、作品は多岐に渡る。1999年日本建築学会賞、2004年度芸術選奨文部科学大臣新人賞などを受賞。主な著書は、『JUN AOKI COMPLETE WORKS Ⅰ:1991-2004』、『同第2巻:青森県立美術館』、『同第3巻:2005-2014』、『原っぱと遊園地』など。